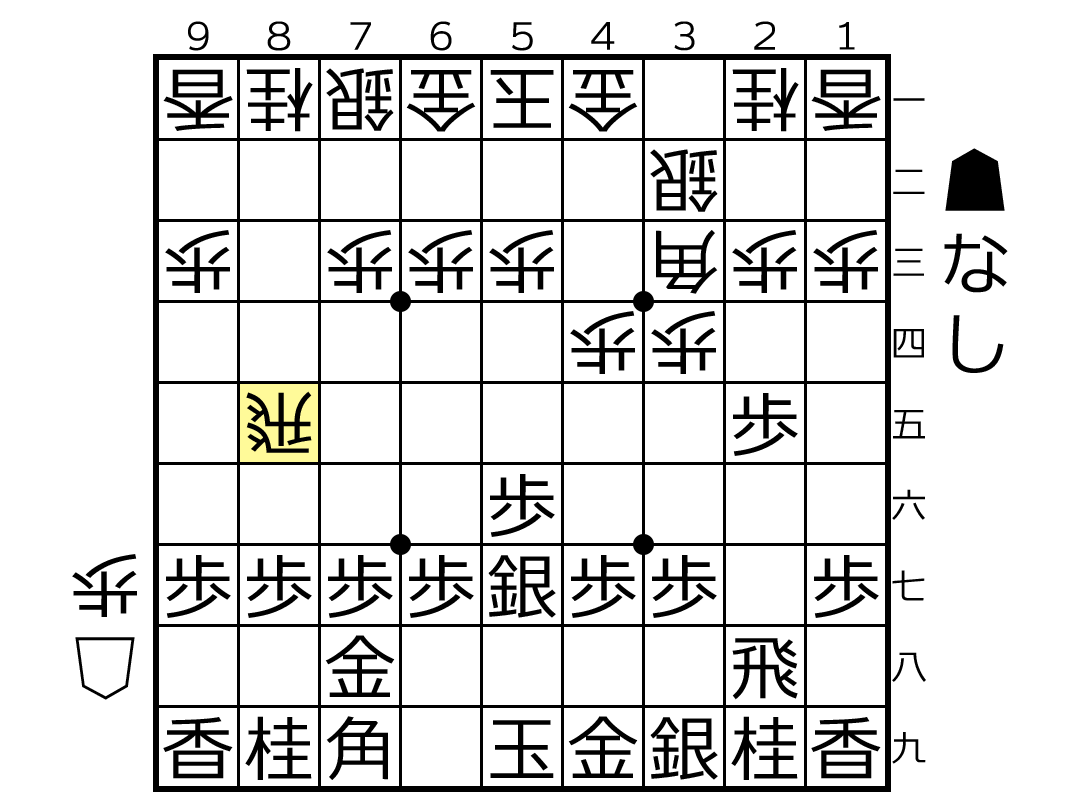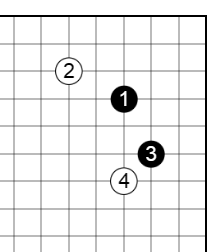分岐図までの指し手
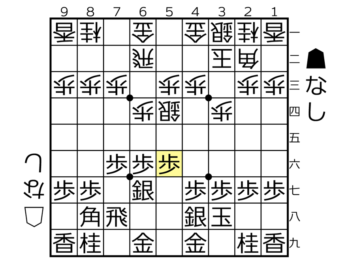
今回は、三間飛車▲6七銀型対右四間飛車の攻防をみていきます。
▲4八銀~▲5六歩は近年指されている形で、崩すのは用意ではありません。
上図以下
△6五歩▲5七銀△6六歩(分岐図)
後手は仕掛けを見送るのももちろん有力ですが、積極的にいくなら△6五歩とここで攻めたいところ。
分岐図では
①▲6六同銀右
②▲6六同角
③▲6六同銀直
の3通りの応手が考えられます。
順にみていきましょう。

分岐①
分岐図以下の指し手①
▲6六同銀右△1四歩▲1六歩 △5二金右
▲6八飛 △1三角▲5八飛 △2四角
▲7八金 △3三桂▲5九飛 △4四歩
▲7七角 △4二金上 ▲5五歩
▲6六同銀右には△1四歩と突いてみたい。
代えて単に△5二金右もありますが、端歩を突かないとその後の指し手に大きな違いが出てきます。
▲6八飛に代えて▲5八金左も考えられますが、△6五銀から銀交換になれば△6九銀の割り打ちの銀をみて後手が指せます。
△1三角は端歩を突いた時からの狙いの一手。
△2四角では△2二角と千日手狙いも有力。
本譜は後手番ながら前のめりな指し方です。

上図以下
△4五銀▲4八金△9四歩▲9六歩
△2二玉▲8六角△3二金▲7七桂
△4二銀▲6五歩△3五歩▲5七銀
△4三銀
△4五銀では△4三銀も有力。
本譜は攻勢の構えで、囲いながらも△3五歩と次に一歩交換をみます。

上図以下
▲4六歩△3四銀引▲5六銀左△4五歩
▲同 歩△3六歩 ▲同 歩 △4五桂
▲6八銀△4六歩(結果図①)
▲4六歩で銀を引かされてしまいますが、△4五歩と仕掛ける余地が生まれます。
結果図は△4六歩のクサビが大きく、後手有利です。

分岐②
分岐図以下の指し手②
▲6六同角 △同 角 ▲同銀右 △3三角
▲7七角
▲6六同角には、角交換してから△3三角と打ちなおすのが有力。
▲7七角では▲8八角も考えられますが、それは角の位置がよくなっているため分岐①より後手が得しています。
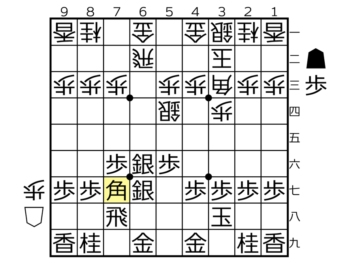
上図以下
△6五歩 ▲5七銀△7七角成▲同 桂
△8九角 ▲8六角△5二金右▲6四歩
△7八角成▲同 銀
△8九角が継続の攻め。
▲6八飛には△6七角成~△6六銀がうるさいです。
▲8六角~▲6四歩が局面を収めにいった構想で、実戦でも指されたことがあります。
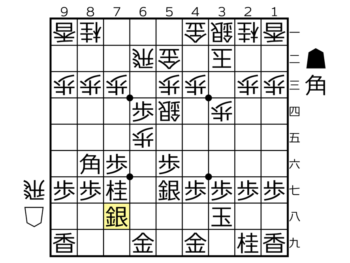
上図以下
△3三桂 ▲4六銀△6六歩▲6八金
△4二金上▲5五歩△4五銀▲5七銀
△3三桂は攻撃的な手で、先手の応手によっては△4五桂からたたみかけます。
▲4六銀は先受けかつ▲5五歩をみた一手。
対して△6六歩が△6七歩成~△8九飛をみたいい歩の突き出しです。
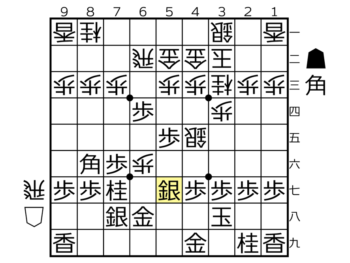
上図以下
△7九飛 ▲8八角△7八飛成▲同 金
△6七銀 ▲6八金△7六銀成▲5八金上
△8七成銀▲7五角△8八成銀▲7一飛
△7六角(結果図②)
△7九飛は▲8八角で飛車が詰んでしまい変調のようですが、△6七銀が意外と受けにくい手で十分手になっています。
△7六銀成~△8八成銀と角を取れば駒の損得としても悪くないです。
結果図は次に△7八成銀をみて後手十分です。

分岐③
分岐以下の指し手③
▲6六同銀直△6五歩 ▲7七銀 △1四歩
▲1六歩 △8四歩 ▲7五歩
▲6六同銀直が最もやっかいな変化とみています。
▲7七銀と引かせて好調のようですが、▲7五歩から形はほぐせるため簡単ではありません。

上図以下
△7二金 ▲5八金左 △4二銀▲8六歩
△3一金 ▲6七歩 △6三金
後手は△7二金と右金の力でサバキを封じたいところ。
△4二銀~△3一金とエルモ囲いにかこい、戦機を待ちます。

上図以下
▲7六銀 △6四金▲2二角成 △同 玉
▲8八飛 △3三角▲7七角 △8二飛
▲3三角成 △同 桂▲7七桂(結果図③)
▲7六銀が▲7五歩と突いた時からの狙いの構想。
▲3三角成に代えて別の手を指すと、△4四歩と角道を閉じられて後手の圧迫作戦でペースを奪われそうです。
結果図はこれからの将棋。
△4四角、△4四歩、△3五角等と手が広い局面でいずれも一局です。